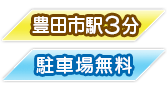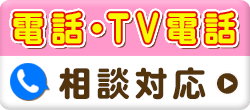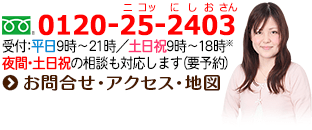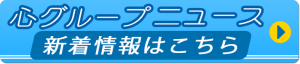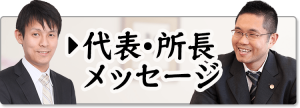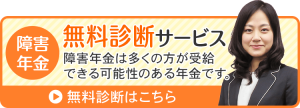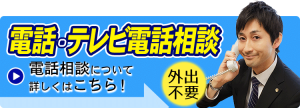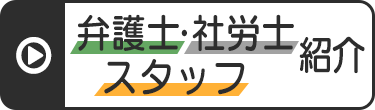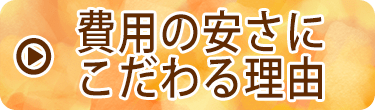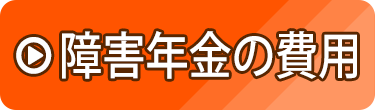統合失調症で障害年金が受け取れる場合
1 統合失調症の症状
統合失調症は、幻覚、幻聴、妄想等の症状が特徴的な精神疾患です。
これらの症状が治まった場合でも、無気力、感情の平板化、認知機能障害等の症状が続くことがあり、治療に長い時間を要する場合があります。
2 統合失調症の障害認定基準
国民年金・厚生年金保険の障害認定基準においては、統合失調症は「精神の障害」に区分されており、例えば以下のような症状が認められる場合、障害年金の受給の対象となりうるとされています。
| 障害の程度 | 障害の状態 |
| 1級 |
高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの |
| 2級 | 残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
| 3級 | 残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの |
3 統合失調症の障害認定に関する考慮要素
統合失調症は予後不良のケースが少なくないため、上記の表に記載した「障害の状態」に該当すると認められるものが多くあります。
しかし、統合失調症は、罹病後数年~十数年が経過している最中に症状が好転することもあったり、逆に急激に増悪し、その状態を持続することもあったりします。
そのため、統合失調症の認定にあたっては、発病時からの療養や症状の経過を十分考慮しなくてはならないとされています。
4 その他の精神疾患との関係
統合失調症とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されることになります。
5 日常生活能力等の判定についての注意点
統合失調症の方の日常生活能力等の判定においては、身体的機能や精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める必要があるとされています。
また、現に仕事に従事している方については、労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものと捉えてはならず、その方の療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断することとされています。
6 申請にあたっての注意点
初診日(統合失調症の症状で初めて医療機関の診察を受けた日)に国民年金に加入していた場合は2級と1級に認定されれば障害年金が支給されます。
また、初診日に厚生年金に加入していた場合は3級、2級及び1級に認定されれば障害年金が支給されます。
統合失調症の場合、妄想や無気力等の症状のせいで、障害年金が受給可能であるにもかかわらず、長い間申請をしていないという例が多くあります。
その場合、初診日に診察を受けた病院にカルテが保管されていなかったり、廃院していたりすることもあり、どのように初診日を証明するかが重要になります。
妄想により、自分が病気であるとの認識に欠けるため、通院を続けられない場合もあり、障害認定日や請求時点での診断書が入手できるかも大事なポイントです。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の種類と金額
- 障害年金は申請してから受給までどのくらいかかるのか
- 障害年金の配偶者加算
- 障害年金の計算方法
- 障害年金における初診日
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の時効
- 介護保険と障害年金は同時に受給できるのか
- 障害年金を受給できる年齢
- 障害年金の種類
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金と生活保護の違い
- 精神障害について障害年金が認められる基準
- リウマチで障害年金が受け取れる場合
- 統合失調症で障害年金が受け取れる場合
- 精神疾患で障害年金を受給している場合の更新時の注意点
- うつ病で障害年金を請求する場合にポイント
- 人工関節で障害年金を請求する場合のポイント
- 眼の障害で障害年金を受け取れる場合
- てんかんで障害年金を請求する場合のポイント
- 心筋症で障害年金が受け取れる場合
- 額改定請求について
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒471-0025愛知県豊田市
西町5-5
ヴィッツ豊田タウン4F
0120-25-2403